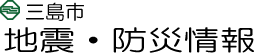避難所運営基本マニュアル(令和4年3月版)
東日本大震災では、地震、津波などによる直接的な災害から助かったが、避難生活等での体調悪化による震災関連死で3,700人以上の方が亡くなられたと言われています。東日本大震災の教訓を生かし、高齢者、障がい者、女性等に配慮した避難所運営を行うため避難所運営のガイドラインとなる避難所運営基本マニュアルを策定しました。毎年、避難所開設訓練や様々な会議での意見を踏まえ更新しています。
マニュアルの特徴
- 東日本大震災の教訓を踏まえ、高齢者、障がい者、女性等の災害弱者に配慮した避難所運営を行えるよう定めたこと
- すべての避難所(23箇所)のレイアウトを策定したこと (避難所別図面、資料)
- 各活動班の役割に優先順位をつけて、実践的なマニュアルとしたこと
- 市災害対策本部、避難所運営本部、自主防災本部との連携を明確にしたこと
- 共通した運営方法と避難所ごとの資料(避難所別図面、資料)を区分したこと
- 初めて見た人でもわかりやすい構成に配慮したこと
令和4年度版の改訂の主なポイント
- 服装の修正(受付時のガウン着用の記述を削除等) 新型コロナウイルス感染症対策編P4
- 資料9「指定避難所一覧」の「中郷中」の対象自治会を「大場(伊豆箱根線路西側)・多呂(風水害時は三島南高等学校)」に変更 資料編P19
- 資料9の下欄に「※風水害時については緊急的に対象避難所以外の避難所へ避難することも可能」を追加 資料編P19
避難所数
23箇所(小学校14校、中学校7校、県立高校2校)
避難所運営基本マニュアル
| 避難所運営基本マニュアル本文 | 避難所運営の基本的内容、各活動班の仕事 |
| 避難所運営基本マニュアル様式編 | 避難所運営に必要な様式、本部へ要請する様式 |
| 避難所運営基本マニュアル資料編 | 運営に必要となる資料、チェックシート、無線使用方法 |
| 避難所運営基本マニュアル 避難所別図面・資料 | 避難所別の運営組織図、避難所レイアウト、防災倉庫の資機材一覧(写真)、発災直後の集合時間・場所 |
| 避難所運営基本マニュアル新型コロナウイルス感染症対策編 | 避難所の開設、受付方法等 |
マニュアルの保管方法
- 各避難所の防災倉庫、市災害対策本部、各学校で保管する。
- 防災倉庫には当マニュアルとともに、使用するための様式(必要部数コピー)、運営に必要な消耗品、レイアウトの部屋名表示、ビブス(役員、市職員用)等を保管する。 避難所運営グッズ
策定の経緯
| 月日 | 項目 | 内容 |
| 平成23年3月11日 | 東日本大震災発災 | |
| 【平成24年度】 | ||
| 4月~9月 | 東日本大震災の教訓の整理 |
|
| 平成24年10月10日 | 第1回女性の視点での防災対策意見交換会 |
|
| 【平成25年度】 | ||
| 平成25年5月~10月 | 第1回避難所運営会議(23回) |
|
| 10月11日 | 第2回女性の視点での防災対策意見交換会 |
|
| 10月~26年3月 | 避難所レイアウト案の検討(23校) |
|
| 10月~26年3月 | 第2回避難所運営会議(23回) |
|
| 3月 | 避難所運営基本マニュアル策定(第1版) | |
| 【平成26年度】 | ||
| 平成26年5月~10月 | 避難所運営会議(23回) |
|
| 11月10日 | 第3回女性の視点での防災対策意見交換会 |
|
| 平成27年5月 | 避難所運営基本マニュアル改訂(第2版) |
|
| 5月~ | 避難所運営会議(23回) |
|