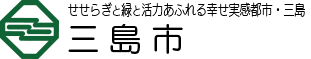下水道事業の用語辞典
下水道事業などで使用する用語の説明(辞典)です。
整備人口・整備面積
下水道を整備した区域内の現住人口及び面積。尚、その数値には、下水道を使用出来る出来ないに関わらない人口及び面積を使用する。
下水道普及率
下水道が使える区域の人口を三島市の人口で除した割合。
管渠(かんきょ)
家庭や工場などから集めた汚水を処理場まで運び浄化する、下水道管とマンホールなどからなる施設で、原則地下にあるものをいう。
処理場
最終的に集めた汚水を処理する施設。
三島市の汚水は、三島市長伏309番地にある三島終末処理場(三島市管理施設)と、沼津市原3060-1にある西部浄化センター(静岡県管理施設)の2箇所で処理している。
三島市の汚水は、三島市長伏309番地にある三島終末処理場(三島市管理施設)と、沼津市原3060-1にある西部浄化センター(静岡県管理施設)の2箇所で処理している。

(写真 三島終末処理場)
大場川
三島市を南北に流れる1級河川。

大場川
三島処理区
三島処理区は大場川西側と大場・東大場地区であり、三島終末処理場で汚水処理をしている。尚、一つの処理場で汚水処理をする区域を「処理区」という。また、単独公共下水道とも言う。
詳細については事業計画を参照のこと。
詳細については事業計画を参照のこと。
西部処理区
大場川東側で夏梅木ポンプ場から北側を西部処理区といい、三島市をはじめ、近隣の沼津市、裾野市、長泉町、清水町の3市2町で構成される広域的な下水道で、沼津市原にある西部浄化センターで汚水処理をしている。狩野川流域関連下水道とも言う。
詳細については事業計画を参照のこと。
詳細については事業計画を参照のこと。
ポンプ場
汚水をポンプにより圧送する施設。
土地の形状等により自然流下(高いところから低い方に流す)が不可能な場合や、自然流下では下水道本管が著しく深くなり、不経済となる場合に設けられます。
市内には三島処理区に南部汚水中継ポンプ場(中261番地3)、梅名中継ポンプ場(梅名322番地3)の2箇所。西部処理区に壱町田中継ポンプ場(加茂川町3930番地15)に1箇所の市が管理するポンプ場があります。
また、西部処理区には夏梅木ポンプ場(三島市谷田625番地1)があり、こちらは静岡県が管理する施設です。
土地の形状等により自然流下(高いところから低い方に流す)が不可能な場合や、自然流下では下水道本管が著しく深くなり、不経済となる場合に設けられます。
市内には三島処理区に南部汚水中継ポンプ場(中261番地3)、梅名中継ポンプ場(梅名322番地3)の2箇所。西部処理区に壱町田中継ポンプ場(加茂川町3930番地15)に1箇所の市が管理するポンプ場があります。
また、西部処理区には夏梅木ポンプ場(三島市谷田625番地1)があり、こちらは静岡県が管理する施設です。
大場川環境基準
大場川には水質汚濁の防止を図る目的で環境基準が定められていて、平成15年に大場川下流の利用目的の適応性が、河川Dから河川Bに引き上げられ、基準が厳しくなった。
大場川水質環境基準 抜粋
大場川水質環境基準 抜粋
| 環境基準 | BOD(高いほど汚い) | 具体的な水質 |
| 河川 B | 3mg/リットル以下 | サケ・アユ等が生息可能な水質 |
| 河川 D | 8mg/リットル以下 | 薬による浄化操作で工業用水として使用可能な水質 |
コミュニティプラント
「コミプラ」や「集中浄化槽」ともいわれる。団地などでよく採用される汚水処理の方法で、各戸で処理すると設置費用が高くなるので共同で大きな処理槽を設け、その地域全体の汚水を処理する。