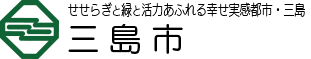令和7年度広島市平和祈念式中学生派遣事業を実施しました
三島市は、昭和34年12月21日市議会において「平和都市(核非武装)」を宣言し、平和都市実現のための事業を実施しています。
この事業の一環として、平成7年度から市内の中学生を毎年8月6日の広島市平和祈念式に派遣しています。これは、三島の将来を担う若い人たちに戦争の悲惨さや平和の尊さについて再認識していただき、そこで感じた思いや経験を多くの人に伝えていただきたいためです。
派遣事業では、平和祈念式への参列や広島平和記念資料館の見学のほか、原爆死没者慰霊碑献花台への献花、原爆の子の像へ折り鶴の奉納、平和の泉への献水、被爆体験講和への参加など、平和への思いを胸に深く刻み込みました。
参加した8人の中学生が、広島市平和祈念式派遣事業を通して感じたことなどを紹介します。
この事業の一環として、平成7年度から市内の中学生を毎年8月6日の広島市平和祈念式に派遣しています。これは、三島の将来を担う若い人たちに戦争の悲惨さや平和の尊さについて再認識していただき、そこで感じた思いや経験を多くの人に伝えていただきたいためです。
派遣事業では、平和祈念式への参列や広島平和記念資料館の見学のほか、原爆死没者慰霊碑献花台への献花、原爆の子の像へ折り鶴の奉納、平和の泉への献水、被爆体験講和への参加など、平和への思いを胸に深く刻み込みました。
参加した8人の中学生が、広島市平和祈念式派遣事業を通して感じたことなどを紹介します。
錦田中学校 2年 石井 有里紗さん

広島駅に着いた時、私は広島の景色に驚きました。街は都会の様にビルが立ち並び、建物の間の綺麗に舗装された街路樹。その道路を走る綺麗な路面電車。本当に80年前に原爆が落とされ、焼け野原になった街とは思えなかったからです。広島の人々は恐怖や絶望にも負けず、広島の街の復興に力を注いだ。それはとても凄いことだと感じました。
第二次世界大戦中、1945年8月6日8時15分。原爆ドームの中心から東南約160メートル付近に原爆が落とされ、悲劇は突然始まりました。
当時中学一年生は、空襲で火が燃え広がることを防ぐ建物の解体作業で、爆心地の近くに集まっていました。その上空600メートルで原爆は目が眩むような閃光を放ち、核爆発を起こしました。爆心地周辺の温度は約3000~4000度にも達していたそうです。爆心地から2キロ以内はほとんど全壊全焼してしまい、崩れた瓦礫の下で炎により亡くなってしまう人がたくさんいました。瓦礫からなんとか這い出た人も皮膚は焼き爛れ、服はボロボロ、体中にガラスが刺さっている人もいれば、目玉が飛び出ている人もいたそうです。水を求め彷徨い、水を飲んだ人は安心して亡くなってしまう。あちこちに転がる死体。誰なのか、性別でさえも分からなくなってしまった人々。その様子を平和記念資料館で見ましたが、当時人々が実際に使っていた物や、焼けただれた衣服など、たくさんの物が展示されており、原爆の熱と爆風がどれほど凄まじかったか、人々にどれだけの苦しみを与えたのか、感じ取ることができ、とても胸が痛みました。当時自分と同じような年齢の人々がたくさん亡くなり苦しんでいる。それを考えただけで辛い気持ちになりました。
講和では、被爆者の梶矢文昭さんが当時の様子を語ってくださいました。梶矢さんは、当時6歳の小学1年生で爆心地から1.8キロの国民学校で被爆し、原爆投下後必死に安全な場所に逃げたそうです。避難した場所に死体や逃げてきた人々で埋め尽くされている中に、ガラス片が大量に刺さり、出血してうめいている母親とそのそばで死んでいる姉がいたそうです。梶矢さんは当時の様子が描かれた絵を見せてくださり、その時の情景が頭に浮かびました。自分が小学1年生なら一人で判断し逃げることができるのだろうか、家族の死を受け入れることができるのだろうか、と考えると胸が張り裂けそうになりました。
あの日から80年経った今も、世界各国で戦争や紛争が続き世界中の核兵器の数は増え続けています。この世には「不要な命」はありません。たった一つの原爆で「平和」や多くの「命」が奪われるのです。世界で唯一の被爆国だからこそ「今」を生きる私達が被爆者達の苦しみ、戦争の恐ろしさ、平和の大切さなどを次の世代へと伝えていくことが大事だと思いました。一人一人が声をあげ、小さなことでも良いので行動に移す、それが世界平和になるために私達ができることだと私は思います。
南中学校 2年 上村 史織さん

被爆者、戦争経験の数は高齢化により、年々減少しており、これから10年後、20年後には戦争について知る機会が少なくなると思います。日本赤十字社の調査によると、核兵器の使用や保有について、約50%の人が「保有も使用もすべきではない」と答えました。それ以外の人は「使用するべきではないが自衛のために保有することは致し方ない」や「保有にも使用にも異論はない」、「分からない」と言う人たちでした。日本で過去にあのような悲劇的なことがありながら、まだそのような考えをする人たちがいることに驚きました。被爆者が減っている今だからこそ、その悲劇を伝えていく使命があることを強く再認識しました。
広島で学んだことを、まずは友達、家族に広めていくことで、みんなの使命感が高まり、平和への一歩を踏み出せるのではないでしょうか。私たちが学んだ小さなことが、世界平和という大きなことにつながっていくと思います。私たちが学び、考えた経験を増やしていくことが、平和への第一歩です。戦争、原爆について知る機会を私たちから増やしていきたいです。そして、原爆がなくなり、平和の灯が消えるその日まで、私たちには平和について考えなければいけない、と強く思いました。
北中学校 3年 嘉山 怜桜さん

私は、小学校の歴史の授業で初めて原子爆弾のことを知りました。そのころの私は「昔の話であって、今起こらないことを考えたって仕方がない。」と思っていました。
しかし、授業の中で広島県に原子爆弾が投下されたこと、その爆弾で多くの人が犠牲になったこと、原爆ドームと呼ばれる建物が焼け残ったことを知りました。私は世界で唯一の被爆国である日本が平和を訴えるきっかけとなった建物や資料館があるのなら、一度行ってみたいと思うようになりました。
私がこの広島派遣事業で特に印象に残っていることは二つで、広島平和記念資料館で見たものと全国こども平和サミットで聞いた被爆者のお話です。
広島平和記念資料館では、実際に焼け残った建物の残がいや名札がついたままの衣服、被爆者が残した言葉などが展示されていました。焼けただれてしまい性別も年齢もわからなくなってしまった遺体の写真や、水を求める人々の絵に言葉が出ませんでした。また、遺体を川から引き上げるために使用されたとび口と呼ばれるくわのようなものや血の付いた担架などが展示されていて、どのように使用したかを想像するだけで血の気が引きました。自分よりずっと幼い子が、いるはずもない両親を探し回ったり、帰ってくるはずもない母親をずっと待っている当時の事態を知り、戦争というものの恐ろしさを改めて実感しました。
全国こども平和サミットでは、被害者の梶矢文昭さんがお話をしてくれました。当時の文昭さんは国民学校一年生、今で言うと小学一年生で、三年生の姉と共に朝の掃除をしていた時に被爆したと聞きました。原爆が落とされてから目の前に広がっていたのはガラス片が体中に突き刺さった母親と瓦礫の下敷きとなった姉の姿、傷を負いながらも救助活動にあたる父親の姿だったそうです。母親は一命を取り留めましたが姉は即死だったようでした。もともと文昭さんの姉は疎開していましたが、死んでもいいから母親と一緒にいたいということで一緒に生活していたそうです。死に際の姉は少しほほ笑んで見えたと文昭さんはおしゃっていました。私はそのことを聞いて、胸がギュッと締め付けられるのと同時に家族の大切さ、今ある日常の大切さを改めて理解しました。そして、原爆が投下された日から八十年という月日が経った今でも苦しんでいる人がいて、思い出すことも辛いのにそれを語り継いでくれている人がいるということにとても感動しました。しかし、日が経つにつれ原爆の経験者はいなくなってしまい、当時の状況を鮮明に知る人はいなくなってしまいます。だからこそ、被爆者から聞いた原爆の恐ろしさを語り継ぎ、風化させないことが大切だと思います。
他の人には経験できないような派遣事業を通して自分が原爆の恐ろしさを知る後継者の1人になれてよかったです。そして、この経験で学んだことを私自身も語り継いでいこうと思います。
中郷中学校 3年 芹澤 虎拍さん

中学2年生後半から3年生の4月まで戦争について学びました。そこで戦争についてもっと知りたい、学んでみんなに伝えたいと思い今回の派遣事業に応募し参加しました。
広島平和記念資料館では実際の写真や様子を表した絵、衣服、遺書、遺品など原爆の被害を物語る品が沢山ありました。見ているだけで胸が苦しくなり、途中からは気分が悪くなりそうであまりじっくりと見ることができませんでした。教科書では原爆が落とされた何万人の命が奪われた。とだけ取り上げており、先生の言葉と文字そして小さな挿絵しかなく、人ごとのように受け取っていましたが、実際に見学し聴き取りしたものは想像を遥かに超えて悲惨なものでした。
僕は日本が受けた傷跡をもっと詳しく伝えるべきだと思います。なぜ広島と長﨑に原爆が落とされたのか、どのような爆発だったのか、被害の様子等、実際の写真をみて心に刻み学ぶべきだと思います。またそれを世界中で実施することで、今より平和になり、現在世界で起きている戦争もなくなるのではないでしょうか。
今年で原子爆弾が落とされてから80年という節目を迎えました。核廃絶を訴え続けている日本被団協は昨年ノーベル平和賞を受賞しました。ですが未だ核兵器も戦争も無くなっていません。1日でも早く平和な世界が訪れるように僕が今できることを積極的に行っていきたいです。
この派遣を通じて学んだことは決して忘れず、もっと歴史を勉強する必要があります。戦争に発展するということはお互いが理解し合えていないということです。世界中の人がお互いを思いやり、助け合い、協力すること、理解しようとすることが戦争がなくなる近道だと思います。
北上中学校 2年 榊原 羽織さん

原爆ドームは、戦争の悲惨さを伝える象徴としての重みを改めて実感させるものでした。特に印象に残ったのは、「核兵器の廃絶」の重要性です。核兵器は戦争の道具であると同時に、人類の未来を脅かす存在であることを学びました。私たちの世代が平和を守るためには、声を上げ、学びを広げていくことが必要だと感じています。学校や地域で平和について話し合いをすることも、その一歩になると思います。
被爆者の方のお話からは、実際に経験した方だからこそ伝えられる現実や思いを知ることができました。被爆者の方が少なくなっている今、私たちがその証言を受け継ぎ、未来へ伝えていく責任を強く感じています。
広島の人々の温かさと平和を願う強い意志に触れ、私も平和を守るために行動したいという思いを持ちました。戦争や核兵器について正しい知識を持ち、周囲に伝えながら、平和な社会の実現に向けて努力を続けていきたいと思います。小さな一歩でも積み重ねることで、大きな変化につながると信じています。
この派遣事業を通じて、私は「平和は当たり前ではなく、努力と願いによって守られるものだ」ということを学びました。未来の世代が戦争の悲惨さを忘れず、平和を大切にする気持ちを持ち続けられるよう、私も学びを深め、行動していきたいです。戦争の悲惨さを胸に刻み、二度と繰り返さない世界の実現に向けて、これからも積極的に取り組んでいきたいです。
中郷西中学校 3年 中川 禅さん

今回の研修で、原爆の恐ろしさや平和の大切さ、戦争の残酷さを改めて実感し、たくさんのことを学びました。この2日間は、平和についてじっくり考える貴重な機会になりました。特に印象に残ったのは、広島平和記念資料館の見学です。社会の教科書の数行では感じ取れない本当に悲惨な姿や写真などが次々と僕の目に飛び込んできて衝撃的でした。僕はこれらを見て、目を背けたくなりました。しかし、目を背けたらダメだと思いました。なぜならこれがかつての日本の姿であり、これを繰り返してはいけない。僕自身、この現実をしっかり受け止め、語り継いでいかなければいけない。その責任があると思ったからです。
資料館を出た後は、胸が苦しくて言葉が出ませんでした。しばらくして「あれは本当の地獄だ」と思いました。日常の中で僕が簡単に使う“地獄”とは比べ物にならないくらい苦しい状況だったことが伝わって来ました。
あの日から80年経った今も、戦争や核問題は世界中で存在し続けています。これからの社会、人工知能や科学技術は日々発展していきます。しかし、それらの技術を戦争や紛争など人々を殺める道具として使ってはいけないと思います。誰も幸せにはならないからです。事実、広島原爆もアメリカの優れた技術を武器に転換しなければ起こりませんでした。
だからこそ、その便利な技術を誰もが人々を悲しませない有効な使い方をすれば世界はもっと平和に向かっていくと思います。そうあってほしいし、僕もそれを訴える1人でいたい。
こんな風に思えるような経験をさせてもらい、感謝したいです。
山田中学校 3年 栗山 翔さん

僕は広島に行き、原爆が落とされた原爆ドーム、戦争や原爆の悲惨さを伝える広島平和資料館を見て、今まで社会の教科書などから見聞きし、想像していたものから180度と言ってもいいほど戦争や原爆に対する考え方が変化しました。
広島平和資料館にて、被爆した人々の絵や写真を見た時は、すぐには理解が追いつかず、見ていられないほどでした。現在の僕たちには想像もつかないような悲劇が現実にあったことを知れたことは、これからの自分を変える大きな経験になったと思います。
自分が大切にしている、僕では家族などの人がいなくなってしまうのは、考えたくもないことです。そんな大切な人が、人が始めた戦争で、人がつくった核兵器でいなくなってしまう戦争を絶対に起こしてはいけませんでした。
それでも、起きてしまったことを変えることはできません。僕たちができることは、亡くなってしまった人々を弔い、今後絶対に日本で戦争を起こさないようにすることの他にないと思います。今回できた貴重な体験を活かして、1人でも多くの人に、戦争の悲惨さと原爆の恐ろしさを伝えていきたいです。
日大三島中学校 2年 吉岡 邑玲さん

広島は、1945年8月6日午前8時15分に世界で初めて原子爆弾が投下された都市です。たった一つの原爆「リトルボーイ」によって一瞬で街が焼き尽くされ、十数万人が命を落としました。被爆直後の市内は、皮膚が焼けただれ、腕から垂らして歩く人々、水を求め川に飛び込み命を落とす人で溢れ、「地獄絵図」そのものでした。式典当日、原爆ドーム前の平和記念公園では、国内外から多くの方が集まり、国内外問わず、忘れてはいけない出来事だと痛感しました。特に私の胸に響いたのは、こども代表の「平和への誓い」です。一言一言にすごく重みがありました。
この訪問で、戦争の悲惨さは、記録だけでは伝わらないことを体験しました。現地に立ち、歴史を自分の事として心に刻み、戦争は過去の話ではなく、今の私たちの選択次第で、再び起こりうる、そう思いました。被爆者の平均年齢は86歳を超え直接証言を聞ける時間は限りがあります。だからこそ私たち若い世代が戦争を風化させないようにしていくことが必要です。
私が広島で学んだことは、「平和をつなぐ責任」です。この思いと学びを胸に平和の尊さを次の世代まで語り継いでいきたいと思います。