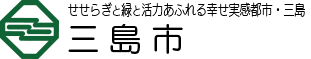市政情報
地勢・歴史(三島の歴史)
新着情報
新着情報はありません。
三島の歴史
- 旧石器時代(1万5000年前まで)
- 飛鳥・奈良・平安時代(6世紀末~12世紀後半)
- 南北朝・室町時代(14世紀前半~15世紀後半)
- 戦国・安土桃山時代(15世紀後半~17世紀初)
- 江戸時代(17世紀初~1868年)
- 明治時代(1868年~1912年)
- 明治時代(鉄道の発達)(1868年~1912年)
- 大正~昭和戦前(1912年~1945年)
- 三島の歴史を紹介します
- 縄文時代(1万5000年~2700年前)
- 弥生時代(2,700年前~3世紀半ば)
- 古墳時代(3世紀半ば~7世紀初め)
- 鎌倉時代(12世紀後半~14世紀前半)
- 戦後(1945~)
- 大正~昭和戦前(軍隊と三島)(1912年~1945年)
よくある質問
- 掲載情報はありません